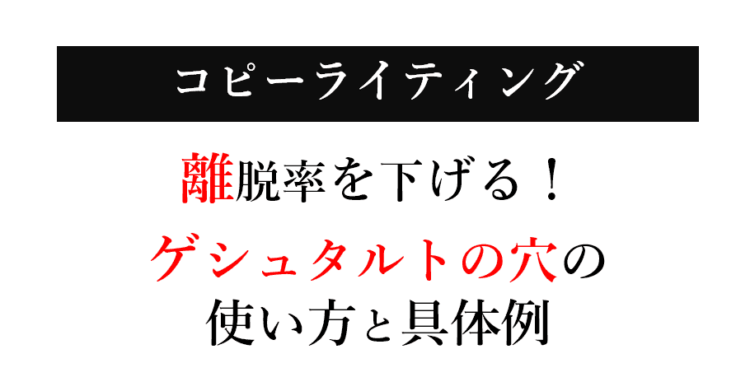
「一生懸命に書いたのに、途中で離脱されてしまう…」
「記事を最後まで読んでもらえない…」
そんな経験、あなたもあるかもしれませんが、ブロガーのほとんどが抱えている悩みになると思います。
これは「文章力が足りない」とか「センスがない」とか、そういう話ではなく、原因はもっとシンプルで、実は「読者を惹きつける小さな仕掛け」 のないことが大きな要因の一つになると思います。
この仕掛けが「ゲシュタルトの穴」 という心理テクニックであり、これを知れば、あなたの文章は今よりずっと「読まれる文章」に変わって行くと思います。
今回は、
- 「ゲシュタルトの穴」って何?
- どうして読者は続きを読みたくなるの?
- 具体的にブログ記事ではどう活かすの?
このあたりを、わかりやすく解説していきます。
ゲシュタルトの穴とは?
まず「ゲシュタルトの穴」とは何かから。
ゲシュタルトの穴とは、
わざと情報を少し欠けさせて、読者の脳に「続きを知りたい」と思わせる技術のこと。
※)「ゲシュタルトの穴」という言葉自体はコピーライターが使う“比喩的な呼び名”。心理学でいうところの 「完結性・閉合の原理」や「ツァイガルニク効果」、「情報ギャップ理論」 を、文章の中で意図的に使ったテクニック、と捉えておくのがよいです。(つまり心理学の用語ではない)
人は不完全な情報や途中で止まったものを見ると、「それを完成させたい」「続きが気になる」という心理が働きます。その“落ち着かない感じ”を、あえて文章の中に作り出すのが「ゲシュタルトの穴」というわけですね。
少し具体例で、この「ゲシュタルトの穴」を見てみましょう。
- 歌のイントロを聞くと、なぜか歌いたくなる
- ドラマを途中まで見ると、続きが気になって仕方ない
- 「ある方法」など、少しだけ隠されると中身が知りたくなる
こうした経験、一度はあると思いますが、これは人間の脳が、「不完全なものを見ると、つい補おうとしてしまう」
という働きを持っているからです。
だから、
- 「イントロを聞く」
⇒ イントロしかないといった不完全なものなので、完全なものにしたくて続きを歌いたくなる。 - 「ドラマを途中まで見る」
⇒ 結末まで知らない不完全な状態なので、落ち着きたいために続きが見たくなる - 「少しだけ隠される」
⇒ 全部を見れてない不安定な状態なので、落ち着きたいために中を見たくなる
こうした、「不完全なもの」を「完全にしたくなる」という脳の働きを利用して、文章の中で意図的に“欠けた部分”を上手につくってみる。すると読者は「完全なものにしたくて」自然とスクロールして先へ進んでくれる、ってわけです。
文章全体を不自然にする必要はありませんが、疑問を持たずに読んでいる文章の中に「穴が空いたように不完全な部分」(ゲシュタルトの穴)を意図的に作る。
これがプロがこっそり使っている、読まれる文章の秘密のひとつってわけです。
ゲシュタルトの穴:普通の文章/失敗例/成功例
「ゲシュタルトの穴」がうまく作られた文章は、読者を「もっと知りたい」という気持ちにさせます。
逆にそうした穴がない文章は、どれだけ良い内容でも、読者から見て(刺激が少ないため)退屈に見える場合も多く、そうなると「途中で離脱してしまう」ことにもなりますね。
ここでは「ゲシュタルトの穴」の使い方がわかるよう、例として「ブログ収益化」「時間管理」「記事の導入文」という、よくあるテーマで、以下3つを比較してみます。
- 「普通の文章」(ゲシュタルトの穴がない普通の文章)
- 「悪い例」(ゲシュタルトの穴を使ったつもりだけどイマイチになっている例)
- 「良い例」(ゲシュタルトの穴を使った良い例)
では1つ目の例、「ブログ収益化」から。
例①:ブログ収益化
① 普通の文章(一般的・情報は完結している)
「ブログで稼ぐためには、毎日コツコツ更新することが大切です。」
- 一般論になっている。読者からは「そんなことは分かってるよ」「当たり前のこと言ってる」としか伝わらず、読んでいても退屈。
- だから読者は新しい情報を求めてスクロールする意欲が弱い
- つまり「続きを読む理由」が少ない文章。
② 悪い例(穴を作った“つもり”だが穴になっていない)
「ブログで稼ぐ人は、あるポイントを意識しています。それは継続することです。」
- “あるポイント” と穴を作り匂わせているが、その後にすぐ答えを出してしまっている
- 「欠落」(穴)が一瞬で埋まるため、ゲシュタルトの穴として機能していない。
③ 良い例(しっかり穴が開いている)
「ブログを1年以上続けられる人は“1割だけ”。でも、その1割が“記事を書く前に必ずやっている『ある作業』”を知った瞬間、私の収益は5倍になりました。」
この文章は、ゲシュタルトの穴があり、更にその穴を強化した例。
- 常識の否定(穴の強化):
「1割だけ」ということで「え?そうなの?」と心理の揺さぶりを置いている。 - 希少性(穴の強化):
「その1割の人だけがやっている」と、「希少性」「価値が高い」「知らないと損」と、ゲシュタルトの穴を強化している - ゲシュタルトの穴:
「ある作業」とは「なんだろう?」と読者の脳に“欠落”が生まれる - 価値(穴の強化):
最後に「収益が5倍」と「その穴を知ることの価値」(続きを読む理由)を強化している。
「常識の否定」とか「希少性」などは、穴の補強(穴が深くなる:より強く穴を知りたくなる)となり、読者の意識は自然と以下のようになることが期待できますね。
- 「その作業って何?」
- 「なんで5倍も収益が上がるの?」
- 「自分もそれ知らないとヤバくない?」
- 「続きを読めば分かるの?なら読む読む!」
上のポイントを簡単に書くと、「穴 × 希少性 × 価値ブースト」の三段構造。
こうした構造で文章を組み立てると、読み進める力が非常に高くなることが感覚的にわかると思います。
例②:時間管理・タスク管理
では2つ目の具体例。
① 普通の文章
「忙しい人は、ToDoリストを活用してタスクを整理しましょう。」
- 「まぁ、そうだよね」「よく聞くよね」という感じで、当たり前と思われて読者の感情が動かない。特に刺激のない退屈な文章。
- 結果、読み流されて終わりそうだし、そもそも読む価値が低いと離脱されるかも。
② 悪い例(穴を作ったつもりの失敗例)
「タスク管理に悩む人には、ある大事なポイントがあります。それは優先順位のつけ方です。」
- “ある大事なポイント” と言いながらすぐ答えが出ている
- 1つ目の例同様、脳が「なんだろう」と思う前に完結してしまう
- つまり、本来の「穴」の効果が出ていない
③ 良い例(読者の脳が“続きを求める”文章)
「1日のタスクが終わらない原因を“時間が足りないから”だと思っている人は多いですが、これは大きな勘違い。
実は、スケジュールを回している人のほとんどが気づいている“ある書き出しの工夫”を知るだけで、作業効率が倍以上になることも珍しくありません。」
- 常識の否定(穴の強化):
「時間が足りないから」と多くの人が信じている前提を覆し、「え?違うの?」と心理を揺らし、ゲシュタルトの穴を強化している - 希少性(穴の強化):
「スケジュールを回している人のほとんどが気づいている」と「できている人だけが知っている」(自分は知らずに損をしている)とゲシュタルトの穴を強化している - ゲシュタルトの穴:
「ある書き出しの工夫」とは「なんだろう?」と読者の頭の中で欠落が生まれる - 価値(穴の強化):
最後に「作業効率が倍以上」と「穴を知ることの価値」(続きを読む理由)を強化している。
これも、最初の例のように、
「穴 × 希少性 × 価値ブースト」の三段構造になってますね。
では以下3つ目の例。
例③:記事の導入文(離脱ポイント)
① 普通の文章
「読みやすい記事を書くには、導入文を工夫することが大切です。」
- 「いや、まぁそうだよね」「それは分かってる...」と、「当たり前」であったり「ありがちなアドバイスだけかな」と思われそう。
- 読者は「はいはい」と思って読み流してしまい、続きが読みたい理由が薄い。
② 悪い例(よくある“穴のようで穴でないパターン”)
「導入文には意外なコツがあります。多くの人はこの部分を見落としていますが、実はちょっとした工夫で読まれやすくなるんです。」
この文章には「意外なコツ」「ちょっとした工夫」と、「ゲシュタルトの穴」があるように見えますが、実はあまり穴になってません。
順番に見ていくと...
- 1)「意外なコツ」「ちょっとした工夫」が曖昧すぎて、穴としては弱い
- この表現だと、読者は「具体的に何の工夫?文章?画像?SEO関係?」と想像が具体的に広がらず、肝心の価値が浮かんでこない。結果、“欠けている情報”にならず、穴として機能しづらい。
⇒ 隠す情報はどんなものかがわかるように具体的にハッキリ伝えるようにする。ただし 正解そのものは言わない
- この表現だと、読者は「具体的に何の工夫?文章?画像?SEO関係?」と想像が具体的に広がらず、肝心の価値が浮かんでこない。結果、“欠けている情報”にならず、穴として機能しづらい。
見直し例)
「導入文を変えるだけで、読了率が2〜3倍に跳ね上がる“ある書き方”があります。」
(漠然とした「コツ」ではなく「書き方」と、「どの部分」「どういう種類の情報か」が示されるので、読者が価値をイメージしやすい=穴になり得る)
- 2)効果が見えないので「読む動機」が立ち上がらない
- 「読まれやすくなる」は抽象度が高く、どれくらい変わるのかが見えない
- 結果として、読者の頭に「今読むべき理由(得する未来)」が作れず、穴が“気にならない欠落”になる
見直し例)
「導入文に“ある一文”を足すだけで、直帰率が◯◯%下がった記事があります。」
(“ある一文”という具体性を持たせ、効果(直帰率が下がる)が同時に見えるので、「え、その一文って何?」と、読者の中に“価値ある欠落”が生まれる=穴として機能する、という感じです)
- 3)文章の具体性が薄くボヤッとしていて、読者の興味をつかめない
- 「何かよくわからない」から「続き読まなくていいや」みたいに思われそう。
- 価値が見えない(何が良くなるのかがよくわからない)
- 自分に関係するのかわからない
- 背景説明がなく説得力が弱い(刺激不足)
見直し例)
「導入文を“ある一文”だけ書き換えたところ、平均滞在時間が30秒から90秒まで伸びた記事があります。特に、最初の3行目に入れた“あるフレーズ”が効いていたのですが...」
(「どの記事の話か」「何を変えたのか」「どんな結果になったのか」が具体的に見えることで、自分にもあてはまるかも、とイメージしやすくなる。また「ある一文」「あるフレーズ」とはどういうものか伏せているので、「それってどんな文?」という価値ある欠落=穴が生まれる)
③ 良い例(穴を生かした文章)
「導入文の“最初の3行”を変えるだけで、読者の読み進み方が驚くほど変わります。実は、多くのブロガーが見落としている“ある書き始め方”というものがあるんですね。」
- 常識の否定(穴の強化):
「最初の3行だけで効果があるの?」という疑問が生まれる。 - 希少性(穴の強化):
「多くのブロガーが見落としている」とはつまり、少ししか知られてないことであり、知っていると優位に立てるといった希少性が感じられる。 - ゲシュタルトの穴:
“ある書き始め方”が隠されているため、価値のある欠落が発生している。 - 価値の提示(穴の強化):
「読み進み方が変わる」=成果が大きい。
だから穴を埋める価値が高く、読者の行動意欲が増す。
こちらも最初の例のように、
「穴 × 希少性 × 価値ブースト」の三段構造にしてみた例。
良い「ゲシュタルトの穴」を作る3つの条件
ここまで具体例を通して見てみると、
「良いゲシュタルトの穴のある文章」には以下の“3つの共通ポイント”があることが分かります。
- ① 常識を揺さぶる(読者の前提を崩す)
- ② 具体的に示しつつ、核心は隠す(価値ある欠落をつくる)
- ③ 穴を埋める価値(効果)を提示する
①から順に少し詳しく見ていきましょう。
① 常識を揺さぶる
まず読者が持っている「当たり前」の考えを少し崩すことで、頭の中に一瞬「え?」という反応が生まれます。
(小さなパラダイムシフトをまず置く、という感じですね)
これはその後に出てくる「ゲシュタルトの穴」をより効果的にする働きがあり、直前にこうした「常識をまず揺さぶる」表現を入れるのがおすすめです。
以下、常識を揺さぶる3つの例。
- 例)ブログが読まれない原因は“文章力”ではありません。
- 例)タスクが終わらないのは、時間が足りないからではありません。
- 例)ブログが伸びない理由は記事数ではありません。
こうした文がまず入っていると、今まで思っていたことと異なることから「え、そうなの?どういうこと?」なんて思っちゃいますよね。
そんな心理的なズレみたいなものが生まれている中で、その後に「知りたいんだけど明確にされてない内容」(穴)があると、「これはなんだろう」という思いがより強くなる(“穴が深く”なる)ってわけです。
※)「ゲシュタルトの穴」の効果がない文章では
常識を揺さぶる内容がなかったり、曖昧だったり当たり前のことしか言っていないかチェックしてみてください。
他にも「意外なコツがあります」「大事なポイントがあります」「ちょっとした工夫があります」といったように、一見ゲシュタルトの穴に見えますが、ただ匂わせているだけになっていないか、もチェックしてみましょう。
② 具体的に示しつつ、核心は隠す
「ゲシュタルトの穴」の一番のポイントは以下の2点。
- 何の話なのか(どの部分の話か)は具体的に示す
- でも核心部分(肝心な中身)はあえて伏せる
例えば以下の文、
- 「導入文の“最初の3行”に、ほとんどのブロガーが見落としている”ある書き始め方”があります。」
- 「ToDoリストの“書き出し方”を変えるだけで、作業効率が倍になります。」
これらの文章では、
- どの部分の話か(最初の3行/書き出し方)→ 分かる
- 何をどうするのか → まだ分からない
という形であり、
読者の頭の中には「え?どんな書き方?どんな始め方?」と、強い興味(価値ある欠落)が生まれます。
※)ゲシュタルトの穴になってない文章では
「意外なコツ」「ある工夫」など何に対するコツや工夫なのか具体性がなく、また、方向性がボヤけていたり、自分に関係があるかわからないような文になっていると思います。また上の方の例で見たように、穴を作ったつもりでその後にすぐ答えを出したりと、穴が一瞬で埋まってしまうような場合もありますね。
③ 穴を埋める価値(効果)を見せる
読者が「続きを読みたい」、つまりゲシュタルトの穴が有効に機能する場合は、
- 知りたいと思える具体的な穴の存在があり、
- その穴を埋めると得られる価値(メリット)が明確であること、
この2つがセットになっているときです。
上の方で見た以下の文章で言えば、
- 「この作業を知った瞬間、収益が5倍になりました。」
- 「最初の3行を変えるだけで、読了率が劇的に伸びます。」
- 「書き出し方を変えるだけで、作業効率が倍以上になります。」
この例では、「具体的な穴(欠けている具体的な情報)の存在」があり、「その穴を埋めることで得られる明確な効果」が見えるため、ここで読者はこう思います。
「そんなに変わるの?これは知りたい!」
「この価値なら、もっと続きを読まなくっちゃ!」
穴が単なる“ただの疑問”で終わらず、
“埋めたい欲求”に変わる(続きを読みたくなる)ってことですね。
※)ゲシュタルトの穴になってない文章ではこの逆で、
知りたいと思える穴があったとしても、その穴が埋まるとどんな効果が得られるのかが明確でないので、自分に影響のあることかがわからず、読む理由が生まれない、みたいな感じです。
穴が弱くなる原因と「読者の思い込み」
ゲシュタルトの穴は、ただ情報を隠せば強くなるわけではありません。
ここまで見てきた、
- 常識を揺さぶる
- 具体的に示しつつ、核心は隠す
- 穴を埋める価値(効果)を見せる
この3つを意識しても、
「なぜか読者が読み進めてくれないな...」
というケースはよく起こります。
このときに見直したいのが、
読者がすでに「これが原因だ」と決めつけている「考え」「思い込み」に触れられているか、という点。
たとえばブログを運営していて、「アクセスが伸びない」「稼げない」「成果が出ない」などの悩みがある場合、文章を読む前からすでに、
- ブログが伸びないのは、文章力が足りないから
- 稼げないのは、まだ努力が足りないから
- 成果が出ないのは、やり方を知らないから
など、「自分なりの答え」を頭の中に持っていることも多いもの。更にここでのポイントは、本人はそうした考えを「正しいもの」だと思っていて、思い込みだとは自覚していない、ということ。
そうした中で、
- 「別の考え方があります」
- 「意外なコツがあります」
- 「ある工夫があります」
など書いても、自分が信じている理由/原因(文章力が足りない/努力が足りない/やり方を知らない)と、何もぶつかっていないので、「ふーん、そういう話もあるんだな」みたいに、軽く流されてしまうんですね。(書いている側は、ここでグッと注目してくれるかな、なんて思ってるんですけど)
同じような文章でも、読者が信じている「理由や原因そのもの」に触れると、一気に反応が変わります。
例えば、
- 弱い例:
「別の考え方、進め方が主流になりつつあります」 - 鋭くした例:
「同じ努力をしても、結果が出る人と出ない人が分かれる“前提”が、すでに変わってきています」
後者では、「考え方が違う」という話ではなく、「今まで信じてきた努力の前提がズレているかもしれない」というところに触れています。
すると読者の頭の中では、
- 「え?じゃあ自分の努力ってズレてる可能性ある?」
- 「今までのやり方、間違ってたかも…」
- 「その前提って何?」
といった反応が自然に生まれます。
この状態になって初めて、ゲシュタルトの穴は「ただの疑問」ではなく、自分の問題として埋めたくなる欠落というものになります。
つまり、穴の強さは表現を強くするかどうかより、読み手が最初から「これが理由だ/原因だ」と思い込んでいる点に、どれだけピンポイントで触れられているかで決まります。
これがズレていると、どれだけ上手に隠したつもりでも、輪郭のはっきりしない穴になってしまう、ってことですね。
穴を強くしようとして失敗するパターン
ゲシュタルトの穴を強くしようとして、
ついやってしまいがちなのが「煽りを足す」こと。
例えば、
- 「このままだと一生稼げません」
- 「9割の人が気づかずに損しています」
- 「今すぐ変えないと手遅れです」
こうした表現、よく見ますよね。
一見すると刺激が強く、
ゲシュタルトの穴を深くしているようにも見えますが、逆に読者の思考を止めてしまうこともあります。
理由はシンプルで、
こうした文章に触れると、読者の頭の中で「大げさじゃない?」「また煽りか…」など、「考える前に防御反応が出る」から。
こう思われた瞬間、読者の意識は「続きを知りたい」から「距離を取ろう」に切り替わってしまいます。
これは「ゲシュタルトの穴」で狙う「強く興味を持ってもらうこと」が、不信感によって上書きされてしまう状態です。
特に、何かを理解してほしい内容(教育や解説記事)では、
- 穴=理解を深めるための仕掛け
- 煽り=行動を急がせるための圧力
この2つを混ぜてしまうと、
文章の役割がブレやすくなります。
では、煽らずにどうやって穴を鋭くするか。
ポイントは、恐怖を足すのではなく、ズレを見せること。
「危ないですよ」と言う代わりに
「今の前提だと、結果が出にくくなっています」と示す、という考え方。
- 人格を否定しない
- 努力を否定しない
- 環境や前提の話にずらす
この形で穴を作ると、「それなら自分も当てはまるかも」「ちょっと続きを見てみよう」など、読者は身構えずに考え始めます。
この状態が、ゲシュタルトの穴が本来狙っている反応になりますね。
- 煽りは一瞬の刺激にはなるが、理解や信頼を積み上げる文章では逆効果になり得るので注意が必要。
- ゲシュタルトの穴を強くするとは、読者を焦らせることではなく、読者が自分でズレに気づける状態を作ること。
- そのために必要なのは、表現の強さではなく、「どの思い込みに触れるか」という判断力
穴を「作らない方がいい」ケースもある
ゲシュタルトの穴を意識する場合、
最初の頃に迷うのが「どこにでもゲシュタルトの穴を入れた方がいいのかな?」ということ。
実際には、
穴を作らない方が文章が強くなるケースも存在します。
穴は作るべきところに作る必要がありますが、この点を意識せず、なんでも「ゲシュタルトの穴を作るぞ」としていくと、
- 読者が混乱する(読み進めづらい文章になる)
- 信頼が下がる(分かりづらい文章になる)
- 「結局なにが言いたいの?」と思われる
といった逆効果が起きやすくなるため、使いどころには注意が必要です。
ここでは具体的に、穴を作らない方が良いケースを見ておきましょう。
① 事実や結論をはっきり伝えるべき場面
例えば、
- 定義の説明
- ルールや手順の解説
- 誤解されると困る注意点
こうしたパートでは、
わざと欠落を作る必要はありません。
本来はそのまま説明すれば十分なところに穴を作ると、「で、結論は何?」「早く答えを言ってほしい」と、読者にストレスを与えるだけの文章になってしまいます。
こうした箇所では「穴を作らない」「最初に結論を言う」「分かりやすさを最優先する」としていく方が、信頼される文章になりますね。
② 読者がすでに不安な状態にあるとき
読者が以下のような心理になっている箇所では、さらに穴を作ると逆効果になることがあります。
- 失敗して落ち込んでいる
- 自信をなくしている
- 正解を探して焦っている
例えば、以下のような表現を結構見かけますが、
- 「実は致命的な落とし穴があります」
- 「ほとんどの人が気づいていません」
すでにその箇所までに読者が「落ち込んでいる」「自信をなくしている」などの心理状態と考えられる場合には、本来の目的となる「続きを知りたい」より先に「怖い」「不安」という感情を余計に強めてしまい、途中で離脱してしまう可能性もあります。
こうした場合には、「まず安心させる」「状況を整理してあげる」のが良く、その上で必要と思われれば、その後で小さな穴を作るという順番がポイントになりますね。
③ すでに「答え」を出すフェーズに入っているとき
記事の後半やまとめ、または「具体的なやり方」を説明する場面では、ゲシュタルトの穴はすでに役割を終えています。
この段階で「実はまだ重要なポイントがあります」「ここからが本題です」といった感じで穴を作ると、単に「引き延ばされている感じ」であったり「売り込み前の匂わせ」とも捉えられてしまうかもしれません。
こうした箇所では、
- 穴を閉じる(謎はもう解き明かす)
- 伏線を回収する(匂わせがあったら、何だったのか明確にする)
- スッキリ終わらせる
こうした文章にすることで、
読みやすく分かりやすい、更に読んだ後の印象が良くなります。
判断のまとめ:作るか迷ったら、ここを見る
ゲシュタルトの穴を作るかどうかで迷ったら、
次の3つを基準に考えてみてください。
- 今の文章の目的は「興味を持たせる」か「理解させる」か
- 読者はいま、不安なのか、余裕があるのか
- ここは話を広げる場所か、まとめる場所か
この問いに対して、
- 興味を前に進めたい
- 読者が比較的フラット
- これから核心に入る
こうした条件がそろっているなら、
ゲシュタルトの穴は有効に機能しやすいでしょう。
逆に「結論を伝える場所」「安心させたい場面」「すでに答えを示すフェーズ」なら、あえて穴を作らない判断の方が、読者が読んでくれる文章になると思います。
ゲシュタルトの穴は「入れるか/入れないか」を機械的に決めるものではなく、
- どの思い込みに触れるか
- 今は揺さぶるべきか、整えるべきか
- 穴を開けるのか、閉じるのか
こうした判断の積み重ねが、読まれる文章を作ります。
この感覚が身につくと、文章を見た瞬間に「ここは穴を作る」「ここは作らない」が、自然に分かるようになると思います。実践の中で色々試してみてくださいね。
【具体例】導入文に応用してみる
では最後に、ブログ記事に応用する具体例として導入文にゲシュタルトの穴を使ってみます。
記事の導入部は、読者が「読み進めるか」「離脱するか」の大きな分岐点。ここでゲシュタルトの穴をうまく使えば、読者の読み進める力が大きくなりますね。
穴がない導入文の例
「多くの人は“文章力がないから読まれない”と思っています。この記事では、ブログで稼ぐための文章術について解説します。」
導入文としては普通であり、特に問題はないと思います。
無理やりゲシュタルトの穴を使う必要もありませんが、この文章は以下になっていると思います。
- 情報が“完結”してしまっている
- 新しい発見や意外性がなく「読む理由」が生まれない
- 核心を隠すこともなく、そもそも“核心そのもの”が普通で薄い
普通の文章なので、先を読む必要性、力が弱く、読者が「ありきたりの記事かな」とおもって離脱する可能性も結構ありそう。
ゲシュタルトの穴を入れてみた例
「多くの人は“文章力がないから読まれない”と思っていますが、実は本当の理由は“文章力そのもの”ではありません。この点に気づいているのは、ごく一部の人だけだと思いますが、実際、その人たちが押さえている“導入文の欠落”こそが、記事が読まれるかどうかの分岐点。
今回は"この欠落とは何か"、"欠落をどう埋めれば読まれる文章になるのか"を解説します。」
実際には段落分けして見やすくしますが、
こんな感じにすると、最初の方でみた例のように、以下の要素が入ります。
- 常識の否定(穴の強化):
「文章力が原因ではない」と前提を崩し、「え?」と心理的な揺さぶりが生まれる。 - 希少性(穴の強化):
「ごく一部の人だけが気がついている」と希少性がある(価値がある)と穴を強化している - ゲシュタルトの穴:
「自分もやらかしてるかも」「欠落って何?」という“価値ある穴”が生まれる - 価値の示唆(穴の強化):
「欠落を埋めれば、読まれるようになるかも」「クリック率・滞在時間が伸びるかも」など、未来を想像させている
こうして見るように、読者の頭の中で“欠落を埋めたい”状態になり、自然とスクロールしたくなる導入文になるってわけですね。
関連)ブログ記事を自然な日本語で書く!読みやすい、分かりやすい文章の書き方のコツ
まとめ
ゲシュタルトの穴はブログの記事だけでなく、各種SNS、メルマガ、広告(レター)、プロフィール文など、どんな文章にも幅広く応用できるテクニックになると思います。
もっといえば、ビジネス上の交渉時、プレゼンなどにも活用できますね。
ブログの活用では、なにか記事を書いた後、
- 記事のタイトルに“ひとつの穴”を入れてみる
- 導入文の最初の3行に小さな穴を仕込む
など、軽く試してみてください。
また読まれる記事を増やしたい、ブログ収益をもっと伸ばしたい方には、メルマガでより実践的な内容をお届けしています。興味があれば、お気軽に登録してみてくださいね。

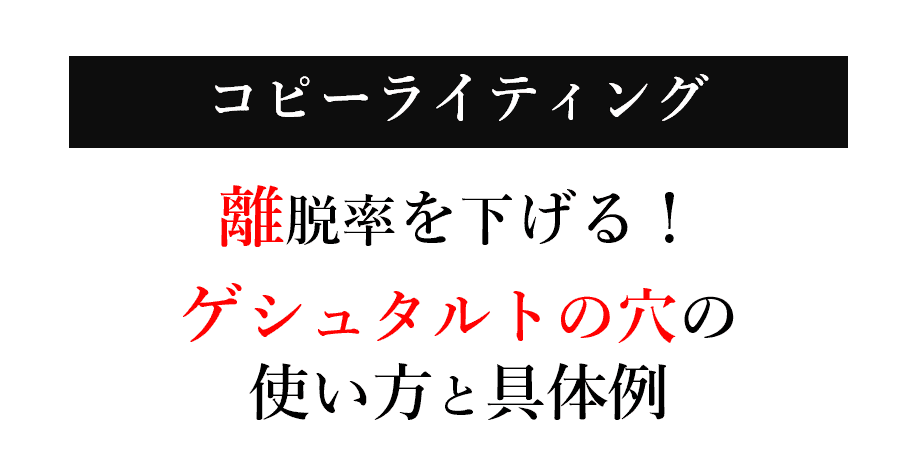
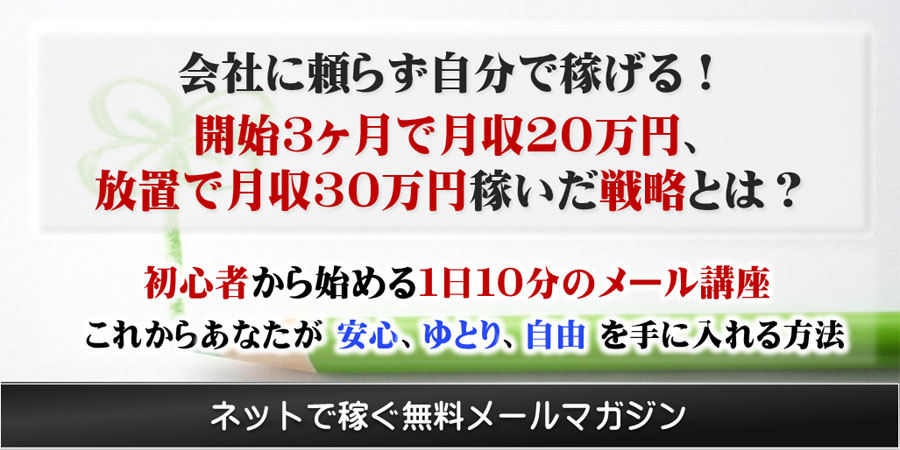
コメント