なかなか給料が上がらない!家計が苦しい!
そんな時、頭に浮かぶのが「副業」ですが、
一般企業でも兼業を禁止しているところは少なくありませんし、これが公務員となれば、さらに厳しく目が向けられます。
公務員がアルバイトや副業をして懲戒処分を受けたというニュースが時折報じられますが、ここでは公務員が副業を禁止される理由やその例外、もし副業をした場合に発覚するのかしないのか、といった点について、詳しく見ていきましょう。
公務員で副業が禁止されている理由
まずは「公務員は副業禁止」と言われる根拠を見ていきましょう。
実は公務員の場合、その活動は法律でしっかりと規定されています。一般企業では就業規則に定められていることが多いですが、公務員はそれが「法律による規定」となる点が特徴です。
主な規定は「国家公務員法」と「地方公務員法」にあります。
国家公務員法の規定
国家公務員法では103条と104条に規定があります。
- (私企業からの隔離)(国公法第103条)
- 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
- ② 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
- (他の事業又は事務の関与制限)(国公法第104条)
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
参照元 国家公務員法
地方公務員法の規定
地方公務員法では第38条に規定されています。
- (営利企業等の従事制限)
- 第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
- 2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
参照元 地方公務員法
これらの法律は公務員の副業を原則として制限していますが、特に地方公務員においては、近年、一定の条件のもとで兼業が許可されやすくなるような運用が一部で進められています。
この点については、次のセクションで詳しく見てみましょう。
禁止の3原則はこれだ!
国家公務員法、地方公務員法、どちらの規定も管轄部門の長に許可を取れば副業も認められそうですが、そこは国に奉仕する仕事の公務員。
許可されるためのハードルは高く、厳格な判断基準があるようです。
なぜこのように副業を原則禁止しているかといえば、理由は以下の3原則に基づいています。これらは公務員としての職務の公共性・公平性を保つ上で非常に重要視されるものになりますね。
- 信用失墜行為の禁止(国公法第99条)
本人は勿論、所属する職場、公務員自体のイメージを壊さない、信用をなくさない為 - 秘密を守る義務(国公法第100条)
本業(公務員)で知った秘密が副業などを通して外部に漏れないようにする為 - 職務に専念する義務(国公法第101条)
精神的・肉体的な疲労などにより、本業に支障が出ないようにする為
これらは一般の会社でも同様のことが言えますが、国や地域に奉仕する役目を負う公務員だからこそ、信用を1mmでも損なうと思われることは一切禁止!と言えるでしょう。
例外はあるのか?
会社の就業規定は各企業独自のものですが、国の法律でその行動が規定されている公務員。原則として副業は制限されていますが、例外規定は存在します。
国家公務員の兼業について
まず内閣人事局・人事院(国家公務員の人事管理をする所)によるは「人事院規則一四―八(営利企業の役員等との兼業」では以下のように規定されてます。
- 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営むこと(以下「役員兼業等」という。)については、人事院又は次項の規定により委任を受けた者は、その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほかは、法第百三条第二項の規定により、これを承認することができない。
簡単に要約すると以下になるでしょうか。
- 公務員が会社役員になったり自分でビジネスをしたりすることは、基本的に禁止
- ただし、自分の仕事に影響がなく、不正な関係もないと人事院が認めた場合のみ、例外的に許可される可能性がある
このほかにも、最近の時流に乗ってだと思いますが、人事院からは「一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)」(令和6年6月)が出され、「兼業またはそれに該当しそうな活動では、以下の内容を参考にしつつ、所属組織の人事担当部局に相談ください」となってます。
主なポイントをまとめてみると以下になります:
まず大切なこと:
- 常勤の国家公務員も、きちんと許可をもらえば兼業ができる場合がある。
- 非常勤職員は基本的には兼業のルールが当てはまらないことが多いようだ(職場ごとの内規は確認が必要)
どんな兼業なら許可が必要になりそうかというと、例えば以下:
- 農業や不動産賃貸(特に規模が大きい場合)
- 大学の先生との兼業や、NPOなど非営利団体での兼業(報酬をもらう場合に限る)
- 研究職の人が自分の研究を活かした会社の役員になるなど特殊なケースも挙げられている
逆に、許可がいらないのは以下のケース:
- 自分の書いた本や作った曲などを単発で売ったり、出版したりして報酬を得る場合。
- YouTubeやブログでアフィリエイト収入を得る場合も、基本的には問題ないとのこと。ただ、やり方や収入の規模によっては許可が必要になることもあるので注意が必要。
- 着なくなった服など、持っていた物をネットで売るような不用品転売も大丈夫。
- 規模が小さければ、不動産の賃貸も許可は不要。
- 資産運用として株式を持ったり売買したりするのも問題なし(インサイダー取引防止などの理由で、職場によってはルールがある場合もあり、確認した方が良い)
- 転勤で空き家になった自宅を貸す場合も、基本的には申請は不要
兼業を始めるまでの流れ:
- まずは、自分の職場の担当部署に相談する
- それから必要な書類を揃えて申請し、審査を受ける
許可が出るかどうかの基準:
- 本業に影響が出ないか、職場との間で変な利害関係が生まれないか、公務員としての信頼が損なわれないか、といった点がしっかり見られる
- 兼業時間も、週に8時間まで、月に30時間まで、平日は3時間までという目安が示されている
より詳細な情報や、具体的な判断については、「一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)」(令和6年6月)ご確認ください。
また、兼業については法律等に基づく規制のほか、所属組織の内規によって制限や手続きが設けられている場合もあるため、必要に応じて所属組織の人事担当部局に確認してみてくださいね。
地方公務員の兼業について
地方公務員の場合は、
総務省から「地方公務員の兼業について」を見るのが分かりやすそうです。
この資料は、総務省が令和6年9月30日に開催された「第1回 地方公務員の働き方に関する分科会」で提示されたもので、地方公務員の兼業制度について詳しく解説されています 。
地方公務員の兼業は、公務の能率確保、職務の公正性確保、職員の品位保持という観点から、原則として任命権者の許可が必要となってるようですね。
主なポイントをまとめてみると以下になります:
兼業をするには、こんな場合に許可が必要:
- 会社などの営利目的の団体の役員などを兼ねる場合 。
- 自分でビジネス(営利企業)を営む場合 。
- 報酬をもらって、何か事業や事務を行う場合 。
許可が出るかどうかの基準は、主に以下の3点:
- 兼業することで本業の効率が落ちたり、疲れすぎた入りしないか。
(週8時間、月30時間、勤務日3時間を超えるようなものは原則許可されない) - 兼業先と自分の所属する自治体との間に、不公平な関係や特別な利害関係が生まれないか。
- 公務員としての信用を傷つけたり、品位を損ねたりするおそれはないか。
特に注目したいのは、社会貢献活動に関する兼業について:
- 最近は人口減少で地域の人材が不足していることもあり、地方公務員が公務以外でも地域のために活躍することが期待される。
- そのため、社会貢献活動に関する兼業の許可件数は増えていて、令和5年度の実績では13,505件と、以前の調査から17%も増えた
- 神戸市のように、地域貢献を目的とした兼業を積極的に後押ししている自治体の事例も紹介されている 。
兼業を考えている皆さんへ大切なこととして:
- 各地方公共団体が、兼業の許可基準を明確にして公表することが推奨されている
- これは透明性を高めて、職員が安心して申請できるようにするため
より詳細な情報や具体的な判断については、「地方公務員の兼業について」を確認してみてください。
また兼業については各地方公共団体で内規や運用が異なる場合があるため、必ず所属組織の人事担当部局に確認することが重要になりますね。
違反するとどうなる!?
もし公務員が申請が必要となる副業を内緒でして、バレたらどうなるのか。
法律で兼業が制限されている以上、許可された範囲を超えて活動してしまったりした場合は、懲戒処分を受けることになります。
具体的には、軽いものだと「戒告」から始まり、「減給」「停職」、そして最も重い「免職」といった処分が考えられます 。
国家公務員であれば国家公務員法、地方公務員であれば地方公務員法に基づいて、それぞれの職場ごとに定められた規程に沿って判断されることになるでしょう。
実際に、これまでにどんなケースで処分が出たのか、いくつか事例を見てみましょう。
- 「許可なし」の不動産賃貸や農業:
昔の事例ですが、さいたま市の職員が許可を得ずに長年水田を耕作していたことで「停職6ヶ月」になったり、堺市では許可なく不動産賃貸で収入を得ていた職員が「厳重注意」を受けたこともあります。不動産の賃貸は、規模によっては許可がいらない場合もありますが、ある程度の規模を超えると許可が必要になるので、無許可で続けていると処分対象になる可能性があります 。 - 無許可のアルバイトや清掃業務:
千葉県の職員が何年も無届けでビルの清掃員をしていたために「減給」処分になったり、大阪市の職員が子どもの受験費用を稼ぐためにパチンコ店の清掃アルバイトをして「停職3ヶ月」になった、といった話もあったようです。これらは、報酬をもらう仕事なのに、きちんと職場の許可を得ていなかったために処分につながってしまった例ですね 。 - 最近増えているネットでの収入:
YouTubeやブログでのアフィリエイト収入、ネットでの転売といった活動で稼ぐ人も増えましたが、これらもやり方や規模、継続性によっては「事業」と見なされ、許可が必要になる場合があります 。もし「これは事業だね」と判断されるレベルなのに、許可なくやっていると、やはり懲戒処分の対象になる可能性があるので、十分な注意が必要です 。
一般の会社員でも副業がバレて処分されることはありますが、公務員は「国民の奉仕者」という立場。その職務の公共性や公平性を守るため、そして何より皆さんからの信頼を損なわないよう、ルール違反には特に厳しい目が向けられる傾向にあります。
もし「副業、どうしようかな?」と考えるなら、トラブルを避けるためにも、必ず事前にご自身の職場の人事担当部署に相談するのが一番。
また上の方で見たように、内閣人事局や人事院、総務省が出しているQ&A集やガイドラインにも詳しく書いてあるので、一度目を通してみるのが良さそうです。
ばれる?ばれない?
公務員が副業した場合、果たしてバレるのか、ばれないのか?!
これは公務員に限らず普通に企業で働く人もそうですが、しっかり確認すれば、ほぼバレます。
というのも、副業で収入を得れば、その分、所得が増えることになりますよね。所得が増えれば、当然、支払うべき住民税の額も変わってきます。
通常、会社員でも公務員でも、住民税は勤務先が給料から天引きして納める「特別徴収」という形が一般的。このとき、職場の給与担当者が、給料に対して算定された住民税額と、役所から通知される住民税額(これは副業の所得も合算された額)を照らし合わせた時、「あれ?この人の税額、給料の割に少し多くないかな?」と気づいてしまう可能性がある、というわけです。
株式の売買や不動産所得など、給与所得以外の収入については、確定申告をする際に住民税の支払い方法を「自分で納付する(普通徴収)」に選択できる場合があり、これを選べば、副業分の住民税は自宅に届く納付書で自分で支払う形になるので、職場に知られるリスクは減るでしょう。
でもこれは「給与所得以外の所得」に限られ、別の会社でアルバイトをして給与を得たような場合は、原則として本業の給与と合算されて住民税が計算されるため、自分で納付を選ぶことはできません。
「バレずに副業をしている人も多いんじゃないか」と考える方もいるかもしれませんが、懲戒処分を受けたというニュースが頻繁に流れないことから、もしかしたらバレずに続けているケースや、発覚しても組織内で内々に処理されているケースもあるのかもしれません。
そうはいいつつも、近年は情報連携も進んでいますし、ちょっとしたきっかけで発覚する可能性は常にあります。例えば、
- 同僚や知人からの密告:
うっかり話してしまったり、SNSなどで活動が知られたりするケース。 - 税金からの発覚:
先ほど出てきた住民税の差額のほか、副業の確定申告をした際に税務署から職場へ問い合わせが入る可能性もゼロではない - 職務専念義務違反:
副業に時間を使いすぎて、本業でミスが増えたり、疲労でパフォーマンスが落ちたりしたことで、周囲から不審に思われることも。
こうしたことも考えられるので、しっかり事前に確認を取ったり、必要に応じて申請を忘れないようにしましょう。
まとめ
- 副業のルールは法律で規定:
一般企業と異なり、公務員の兼業は法律で原則が定められている - 禁止の理由は「3原則」:
「信用失墜行為の禁止」「守秘義務」「職務専念の義務」を守るため。 - 例外には必ず許可が必要:
不動産賃貸や社会貢献活動など許可されやすいケースもあるようですが、任命権者の許可が不可欠。 - 違反すると懲戒処分も:
無許可での兼業やルール違反は、戒告から免職まで、重い処分の対象となる。 - 副業は「ほぼ確実にバレる」:
収入が増えれば税金(住民税)で発覚する可能性が高く、同僚からの情報など税金以外のきっかけでバレるリスクもある
今後を考える
過去の例を見れば、公務員をしながら作家の仕事をしていたりと、副業もその種類は勿論、許可を与える人の理解の深さ、度量の広さがどれほどあるかにも大きくかかっていそうです。
公務員であれ普通の企業にお勤めの人であれ、現在の延長線だけを見ながら進んでいく、現状維持だけしか道はない、となると、少子高齢化にともなう国力低下、経済の先行き不透明感などから、後々つらい状況にもなることも考えられそうです。
少しでも経済的に安定する方向にもっていくには、新たな収入源を考える必要性も今まで以上に高まっていると思います。
承認が取れる取れないもあると思いますが、
必要であれば是非その必要性を訴えて前向きに考えていきたいところです。
現在私は自分の体験を通し、こうした先を見越して何かしなければ、と考えている人向けに無料のメールマガジンを配信しています。
詳しくは以下をご覧ください。


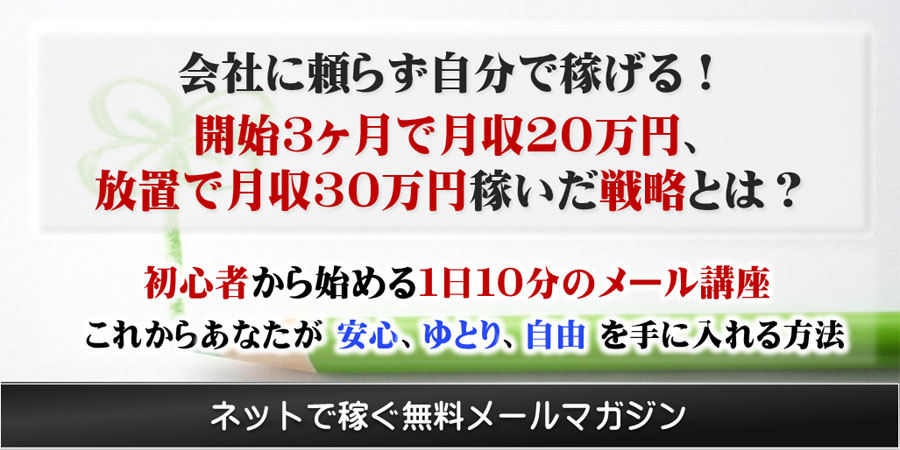
コメント