「頑張っているのに、なぜ給料が上がらないんだろう?」
多くの会社員が抱えるこの悩み、物価上昇が続く今、ますます深刻になっていると思います。会社に任せていれば給料が上がるといった時代は終わり、自分自身の頑張りだけではどうにもならない構造的な問題があるのかもしれません。
この記事では、給料が上がらない理由を「個人の問題」と「会社の仕組み」の両面から掘り下げます
単に現状を嘆くのではなく、これからの時代に合った「未来のための稼ぎ方」まで視野を広げ、あなたの収入の可能性を広げるヒントをお届けします!
給料があがならい理由とは
会社で給料が上がらない理由は、いくつかの複雑な要因が絡み合ってることも多いですが、大きく分けると以下の3つの視点から考えることができます。
- 個人の問題: あなた自身のスキル、働き方、そして考え方。
- 会社の仕組み: 企業の評価制度、組織体制、そして経営状況。
- 社会・経済環境: 日本全体の景気、業界の動向、そしてグローバルな潮流。
これらを1つ1つ掘り下げていくと、
「なぜ給料が上がらないのか」という理由も分かってくると思います。
1)個人の問題について
給料が上がらないと感じる時、まず向き合うべきは自分自身の考え方や行動かもしれません。
会社は、成果や貢献に対して対価を支払う組織です。残念ながら、あなたの「頑張り」が必ずしも「給料アップ」に直結しないのは、その頑張りが会社の求める方向とずれていたり、貢献したとはとらえられてないかもしれません。
私は会社では新人から管理職まで経験してますが、経験上、給料が上がりにくいと感じる人には、いくつかの共通した思考パターンがあるようです。
もし、心当たりのある点があれば、少し立ち止まって考えてみても良いかと思います。
「給料が上がれば頑張るのに」という「条件付きの努力」
「給料があがれば働くよ」といういう人がいます。
つまり、給料があがらないから能力を発揮していない、本当はもっとできるけどこんな給料じゃやる気にならない、という人です。
こういう人は絶対給料上がりません。
というのも、会社はどういう人の給料を上げるのか、給料を与える側の立場に立った考えを持たないからです。
子供の話に例えてもなんですが、自分がお父さん、お母さんだったら、どんな子供にお小遣いあげたいですか? お小遣いくれないから何もしない、っていっている子にあげたいと思うでしょうか?
お小遣いなんてなくても進んで色々お手伝いする子や勉強をする子、そういった子供だからこそ、親も色々してあげたいと思うのです。
会社でも同じこと。給料がたとえ低くても、進んで何かをやろうとする人、自ら学んで積極的に動ける人、こういう人がまずは次の昇給対象者となっていくのです。
特に自分のことだけを考えるのではなく、周りに影響を及ぼしながら働ける人、こういう人は誰かが必ず見ていて、上に引っ張り上げようと狙われる人ですね。
- 30万円の給料が欲しければ、そのレベルの人達が出す成果を自分も継続的に出し続ける
- 50万円の給料が欲しければ、同じように、そのレベルの人達が出す成果を自分も継続的に出し続ける、
こうした姿勢や行動が必要です。
そのレベルの人達がどういった仕事をし、どういった成果を出しているのか、理解して進んで実践することが昇給につながります。
「頑張ってます」のアピールだけでは不十分
やたらと頑張ってますという人や、頑張っているアピールをするタイプ。こういう人も中々給料が上がらないかもしれません。
確かに頑張ることは大切です。
でも頑張ってるのは皆同じ。少し厳しく言う人にかかれば、頑張るのは当たり前、とすぐ言われます。
会社にとって重要なのは、その頑張りがどれだけ会社の利益に貢献したか。
こうした人も会社から見たらどう見られているか、一度考えてみた方がよいでしょう。
例えば、長時間働いて頑張っているとしても、それが非効率な作業の結果であれば、会社にとってはプラスというよりマイナスにもなりかねません。
重要なのは、「どれだけ時間をかけたか」などではなく、「どれだけ価値を生み出したか」。
自分の頑張りが具体的な成果や利益にどう繋がったのか、数字や具体的なエピソードで語れるように意識してみましょう。
「私はもっと評価されるべき」という視点のズレ
私はもっと評価されるべき。私の上司は見る目がない、などとお嘆きの貴方。
こうした考えの方もいるでしょうが、どう評価されるべきとお考えなのか、また、その評価はどういった基準のものなのか、一度冷静に考えても良いと思います。
会社の基準は「利益をあげること」であったり「利益をあげることに貢献すること」。ハッキリ言ってしまえばそれが全てです。
自己満足で終わっている仕事はないか、自分の業務が最終的に会社の売上やコスト削減、顧客満足度向上にどう結びついているのか、冷静に見つめ直すことが給料UPにはとても大切なこと。
会社が求める「成果」を理解し、そこに自分の力を集中させることが、評価へと繋がる近道になると思います。。
評価される人、されない人
結局のところ、給料を上げるためには、会社から「評価される」ことが不可欠です。
評価される人というのは、単に与えられた仕事をこなすだけでなく、「どうすれば会社や部門、チームに貢献できるか?」という視点を持っているものです。
そうした視点を持つ人は、自身のスキルアップを怠らず、新しい知識を積極的に学び、困難な課題にも前向きに取り組む傾向があります。その姿勢と行動が結果的にその人の能力の底上げとなり、会社からも「この人に任せたい」「この人をもっと引き上げたい」と思わせる存在になるのです。
給料が上がらないと嘆く前に、
まずは「どうすれば貢献できるか」という思考に切り替えていきましょう。
会社の問題:見えない壁と構造的な課題
会社側の要因も給料が上がらない大きな理由となり得ます。
企業を取り巻く環境は常に変化しており、時には個人では太刀打ちできない「見えない壁」が存在することもあります。
ここでは、会社が原因で給料が上がりにくい3つの主要な構造的問題を見ていきましょう。
1. ポストの飽和とキャリアパスの閉塞
会社で給料が上がるというのは、多くの場合、昇進とセットです。
私の場合も新人から管理職まで昇進を重ねて経験してますが、その中で多くの社員を見て感じるのは、どんなに頑張っている人でも、上のポストが空いたり、あらたな部署が新設でもしない限り、昇進はなかなか望めるものではないということ。
これは、個人の努力ではどうにもならない、会社全体の課題になりますね。
特に今の時代は、組織のスリム化であったり、事業の成長が停滞している会社では、新しい役職が生まれにくくなっています。昔のように勤続年数が長ければ自然と昇進できた時代というのは、事業が拡大し、部署の新設なども多く、昇進するポストが増えていったので自然に初診で来てたと思います。
でもそんな時代はとっくの昔に終わってます。
優秀な社員がいても、上が詰まっていることで上のランクに行けずに力を発揮しきれない。そんな閉塞感を抱えている部門や会社員は少なくないでしょう。
これは、個人のがんばりだけではどうにもできない、まさに「見えない壁」なんです。
2. 企業の業績不振と分配の限界
給料の上がらない最もシンプルな現実は、会社そのものの業績が悪いこと。
会社が赤字であれば、人件費は真っ先に削られる対象になります。そうなると、昇給どころか、給料カットやボーナス激減を経験した人は山ほどいるでしょうし、ニュースでも時折話題にもなりますね。
(昇給以前に、リストラ、ということにもつながります)
ご存じのように、会社が得た利益は、社員の給料や今後の事業への投資、株主への配当など、様々なところに分配されます。でも十分な利益がなければ、社員一人ひとりに十分な給料を支払う余裕などは当然ありません。
どんなに個人が頑張って成果を出しても、会社の「パイ」そのものが小さければ、分配される分も限られてしまうという現実。
これは、一社員の力だけではどうにもならない、重い構造的問題と言えるでしょう。
3. 所属部門の業績低迷
また仮に会社全体としては黒字でも、あなたが所属する特定の部門や事業が不振であれば、それが給料に響くことはよくあります。
これは私自身も目の当たりにしてきたことです。同じ会社なのに、利益を上げている花形部署と、そうでない部署では、ボーナス査定や昇給スピードに明確な差が出る場合がありますね。
会社の利益は、各部門の貢献度によって左右されます。不採算部門にいると、たとえ個人が優秀なパフォーマンスを発揮していても、部門全体の評価に引きずられてしまい、給与水準が上がりにくい、あるいは他の部門に比べて昇給が遅れるという場合もありえます。
この状況を打破するには、自分のスキルを活かして部門の立て直しに貢献するか、あるいは成長が見込める他の部門への異動、さらには転職といった、一歩も二歩も踏み込んだ考えや行動が必要になるでしょう。
それでもやっぱりサラリーマン
「給料は簡単には上がらない」。これは、残念ながら多くの会社員が日々実感している厳しい現実だと思います。
社員はあまり気にしないと思いますが、特に大企業になればなるほど、多くの社員を抱える組織として、全員に十分すぎる給料を与え続けることは、企業の存続を脅かすことになりかねません。
(減税や保険料に引き下げなどに躍起になっている今の日本の現状が、これと同じにならなければ良いですけど)
会社は、継続的に事業を回し、その中で社員のモチベーションを維持するために、資格制度や昇進制度を設けています。そうし中でも係長、課長、部長と上に進むにつれて、ポストの数は限られ、まさに「狭き門」となります。
私も会社時代、実力があるのに「なぜこの人は昇進しないんだろう」という人も結構見てきましたし、「万年平社員」「万年係長」といった言葉が生まれるのも、こうした日本の企業の構造的な課題を示していると言えます。
日本の経済が急速に成長していた時代は、事業規模の拡大に伴い、新しい役職やポストがどんどん増えていきました。だから、とにかく真面目に働いていれば、いつかは昇進して給料もボーナスも上がるという好循環があったものですが、そんな時代はもう何年も前に終わっています。
今、サラリーマンが置かれているのは、経済成長が鈍化し、変化のスピードが加速する時代。この環境変化をしっかりと見つめ、その上で次の行動を考えことが兎に角重要になってきているのがまさに今とこれからになるでしょう。
給料、ボーナスがあがるときとは
では、どのような時に、給料やボーナスは上がるのか。
実は明確な基準がある場合と、会社全体の状況に左右される場合の2つがあると思います。私自身の経験や、これまでの企業活動を見てきた中で、おおよそ以下のポイントが挙げられるでしょう。
1. 給料(基本給)が上がる時
基本給、つまり毎月の給料が上がるのは、一般的に「職務遂行能力」や「会社への貢献度」が継続的に評価された時です。
これは、半年から1年といった期間で個人の出した成果が認められ、人事評価制度に基づいてあなたの「等級(資格)」や「役職」が上がった時に実現します。
会社によって評価の仕方も、相対評価、絶対評価、といった違いもあるでしょうが、継続的に会社の利益に貢献し、何期か連続して常に良い成績、評価されると、「この人にはもっと重要な仕事を任せたい」「この役割に見合った対価を払うべきだ」と会社側が判断します。
特にまだ部長や役員という大きな役職ではなく、係長、課長補佐、レベルへの昇進であれば、部内で課長が集まり、期ごとに評価のバランスをとるための意識あわせをする場合もあるかもしれません。
そうした時に毎回必ず名前の挙がる人は、社内の覚えも良く、近々昇進していく人にもなりますね。
会社が給料を上げる場合は、「未来への投資」として、成長が見込める人を挙げていく、というところを意識していくのが良いと思います。
2. 賞与(ボーナス)が上がる時
ボーナスは、給料とは少し性質が異なります。これは個人の成果に加え、所属する部門や会社全体の業績が大きく影響する部分です。
私も会社員時代、「今年は会社の業績が良いからボーナスが増えるぞ!」と期待したことも結構ありました。
個人の頑張りが評価されるのはもちろんですが、それ以上に、会社全体で目標を達成したり、市場で大きなシェアを獲得したり、予想外の大きな利益が出た際に、その「おこぼれ」として社員全体に還元される色合いが強いのがボーナスなんですね。
特に日本の多くの企業では、ボーナスは会社の利益を社員と分かち合う性格が強いので、自分の力だけでなく、チームや組織がどれだけ儲けたかが大きく関わってきます。
どうすれば1万円給料があがるのか
ここまで見てきたように、会社で毎月の給料を1万円、2万円と上げることは、決して簡単なことではなく、年単位の時間がかかる場合も多いですね。
年功序列や終身雇用が崩れてきている現状、長年かけて少しずつ積み上げ、役職を上げていくという従来のキャリアパスだけでは、期待通りの収入アップは難しい時代になってます。
会社という組織の構造上、一人の給料を1万円上げるためには、評価制度の中で一定の成績を継続的に出し続け、昇格や昇給のタイミングを待つ必要があります。これには、かなりの時間と労力がかかりますし、正直なところ、努力に見合うリターンが得られないことも珍しくないかもしれません。
では、もっと手早く、確実に収入を増やしたい、と考えた時、どうすればいいのでしょうか?
私の考えとしては「会社の給料アップ」以外の選択肢に目を向けることが、今の時代を生き抜く上で非常に重要だと考えています。
たとえば、月に1万円、2万円の収入アップであれば、「副業」は非常に現実的な選択肢です。
近年、働き方改革や多様なキャリア形成の推進により、副業を認める企業が格段に増えてきました。Webライティング、プログラミング、デザイン、オンラインでのスキルシェア、あるいは少額の投資など、個人で始められる副業の種類は多岐にわたります。会社での昇給を待つよりも、はるかに短い時間で、直接的に収入を増やすことができると思います。
さらに、月に5万円、10万円といった大きな収入を目指すのであれば、「ネットビジネス」など、時間労働の延長ではない、仕組み化された稼ぎ方を学ぶことも視野に入れるのが良いと思います。
これは敷居が高いと感じるかもしれませんが、一度軌道に乗れば、給料では得られないような自由な稼ぎ方につながる可能性もあります。
会社の給料が上がらないと嘆くだけではなく、「では、どうすれば収入を増やせるんだろう?」という別の視点を持つことが、これからの未来を切り拓く第一歩になりますね。
まとめ
- 給料アップは、個人の考え方や仕事への貢献度を見直すことから始まる
- 会社の構造的な問題(ポスト不足、業績不振など)も、昇給を阻む大きな壁
- 会社任せでは難しい時代。給料アップには時間と労力がかかることも多い。
- 今の時代、副業は収入アップの現実的な選択肢であり、その可能性は広がっている
会社の給料だけを頼りにするのは、ますますリスクが高い時代になってきました。
私自身も長年サラリーマンとして給料の壁を感じ、その後は早期退職、海外でネットビジネスをスタートさせた経験があります。
この変化の時代だからこそ、自分のキャリアや収入について今まで以上に考えて行動することが、とても重要になってきていると思います。この記事が、あらためて未来を見つめ直し、一歩踏み出すきっかけになれば幸いです。
今後を考える
少しでも上がって欲しい給料ですが、なかなか上がらないな、と考えている内に時間だけが流れ、気が付けば半年、1年と過ぎていく、という経験をしている方も多いと思います。
今までは会社だけで収入を得て生きていく、収入を得るのは会社からだけ、といったことをまるで常識のように考えていたかもしれませんが、少しでも経済的に安定する方向にもっていくには、新たな収入源を考える必要性も今まで以上に高まっているでしょう。
現在私は自らの体験を通し、そうした先を見越して何かしたいと考えている人向けにメルマガを配信しています。
詳しくは以下をご覧ください。


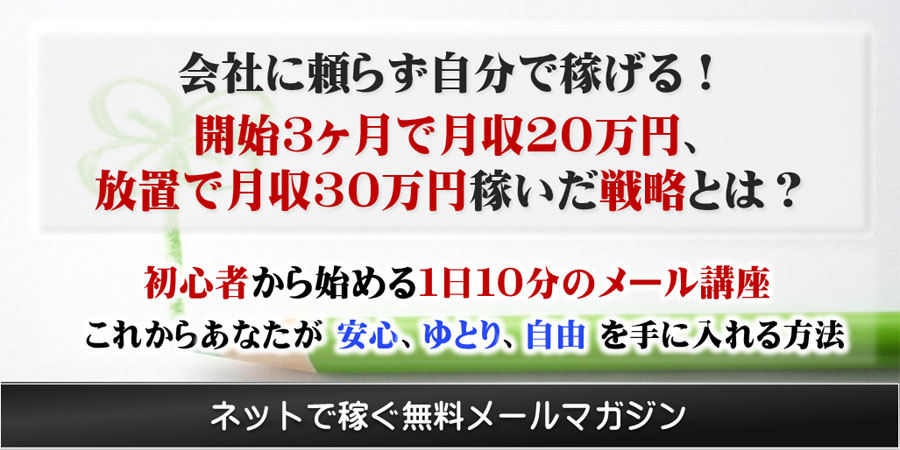
コメント