給料日と言えば、10日、15日、20日、25日と、5の倍数の日が思い浮かびますが、公務員の給料日はいつなのか。また公務員以外に世間一般的には給料日はいつが多いのか、ちょっとここで見てみましょう。
公務員には国家公務員、地方公務員とありますが、給料日は国家公務員であれば人事院規則、地方公務員であれば知事が定める日、人事委員会規則で定める日、など、条例によりしっかり決まってるんですね。
公務員の給料日
公務員の給料日はいつか?
法律的に見れば労働基準法(第二十四条)には「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」という規定はありますが、「何日に支払うこと」というところまでは定められてません。
ということから実際はどうなのかと見てみると、まず国家公務員であれば各省庁によって異なります。また地方公務員であれば各自治体(都道府県、市町村)によって異なります。
順番に国家公務員から詳しく見てみます。
国家公務員の給料日:16日、17日、18日
国家公務員の給料日は人事院規則九―七(俸給等の支給)にて、16日、17日、18日と定められてます。
具体的には以下のようになってますね。
別表(第一条の四関係)
|
職員の属する組織の区分 |
支給定日 |
|
会計検査院 |
16日 |
|
人事院 |
|
|
内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。) |
|
|
内閣府本府 |
|
|
宮内庁 |
|
|
公正取引委員会 |
|
|
国家公安委員会 |
|
|
個人情報保護委員会 |
|
|
カジノ管理委員会 |
|
|
金融庁 |
|
|
消費者庁 |
|
|
こども家庭庁 |
|
|
デジタル庁 |
|
|
総務省(公害等調整委員会を除く。) |
|
|
公害等調整委員会 |
|
|
法務省 |
|
|
外務省 |
|
|
財務省 |
|
|
文部科学省 |
17日 |
|
厚生労働省 |
16日 |
|
農林水産省 |
|
|
経済産業省(特許庁及び中小企業庁を除く。) |
18日 |
|
特許庁 |
17日 |
|
中小企業庁 |
|
|
国土交通省 |
16日 |
|
環境省(原子力規制委員会を除く。) |
|
|
原子力規制委員会 |
18日 |
|
防衛省 |
引用元:人事院規則九―七(俸給等の支給)
また上で見る給料の支給日が、土曜、日曜の場合は金曜日、支給日が休日の場合には翌日になると定められてます。
ただし、支給日が休日で、その翌日が19日になった場合には15日になるとも定められてます。
この「19日を避ける」というのは特殊なルールになりそうですが、システム上の都合や事務処理をする上での例外的な措置なのかもしれません。
しかし、規則でビシッと決まっているものなんですね。調べてみてちょっとびっくりしました。
地方公務員の給料日:21日が多いとされるがバラバラ
続いて地方公務員の給料日です。
地方公務員では「地方公務員 給与 条例」で検索すると給与に関する条例が色々と出てきますが、例えば以下などがありますね。
- 職員の給与に関する条例:東京都(第七条)
- 給料の支給日は、給与期間のうち知事の定める日とする。
⇒ 職員の給与に関する条例施行規則 第二条:条例第七条第二項に規定する給料の支給日は、十五日とする。十五日が日曜日、土曜日又は休日(中略)に当たるときは、十五日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。
- 給料の支給日は、給与期間のうち知事の定める日とする。
- 給与条例:名古屋市(第七条)
- 給料は、月の初日から末日までの期間について管理者が定める支給日にその月額の全部を一回に支給する。
⇒給与条例施行規則 第一条の五: 条例第七条に規定する給与期間についての給料支給日は、その月の十六日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
- 給料は、月の初日から末日までの期間について管理者が定める支給日にその月額の全部を一回に支給する。
- 職員の給与に関する条例:大阪府(第九条)
- 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち人事委員会規則で定める日とする。
⇒人事委員会規則 第三条:条例第九条第二項の規則で定める給料の支給日は、十七日(その日が土曜日に当たるときは十六日、日曜日又は休日(中略)に当たるときは十八日(その日が休日に当たるときは十五日))とする。
- 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち人事委員会規則で定める日とする。
- 福岡市職員の給与に関する条例:福岡市(第7条)
- 職員の給料は、その月分をその月の20日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日にもっとも近い日曜日、土曜日及び休日でない日)に支給する。
このように、自治体が各々で定めてます。
上で見た4つの都府市では15日、16日、17日、20日と支給日もバラバラでしたが、三菱UFJニコスの情報では、地方公務員の給料日は21日が多いとなってますね。
一般の会社は25日?
銀行に勤めていた方の話や、上に出てきた三菱UFJニコスの情報からすると、一般企業世間一般的には「25日の給料日」が一番多いそうです。
私の場合も、海外移住前に日本で働いていた会社も確かそうだったと思います。あなたの会社はどうでしょう?
なぜ25日が多いかと言えば、以下の理由からのようですね。
- 月末にすると、年末などでは難しくなる
- 2月は基本28日まで。
- 月初にすると、5月の連休などが変則になる
- 給料日は基本覚えやすい5の倍数の日
こうした理由だとすると、給料日の候補は10日、15日、20日、25日となってきますが、これに昔の習慣や実際の実務上にかかる時間が影響してそうです。
- 昔はまだ勿論パソコンとかもない
- 月初は10日ぐらいまで何かと忙しい
- 給与計算は10日ほどかかる
これらから考えると、10日~20日の間に計算やらなにやらしなければならず、結果「25日が最も良さそうな候補日」となりますね。
給料日の分散はしないのか?
多くの方が経験されていると思いますが、毎月給料日(25日か、25日が週末の場合は直前の金曜日)にはATMや銀行は大賑わい。
お盆休みも混雑回避のためにずらして取得する昨今ですが、なぜか給料日については最も人気な25日からずらして混雑を緩和する、という動きがとられません。
最も大切な給料日が変わるとなると、給料を出す側も受け取る側も結構な衝撃があって大変そう。また商店街などでセールス日の設定も複雑になって、商売的にも影響がでるかもしれませんね。
ちなみに銀行はどうかといえば、さすがと言うかやっぱりと言うか、忙しい25日は避けて10日が多いみたいです。
公務員の給料日まとめ
- 国家公務員:各省庁ごとに16日、17日、18日と決まっている
- 地方公務員:各自治体(都道府県、市町村)で各々決められている。東京、名古屋、大阪、福岡と調べてみると15日、16日、17日、20日となっているが、全体的には21日が多いらしい
- 一般の会社では25日が多いと言われている
とても楽しみな給料日。
さて今月の給料、どうでしたか?
今後の展開
このブログにもたびたび登場するお給料。
景気がなかなか上がらない、でも物価は上がる、といった辛い状況が続きますが、安定していると思われる公務員も、このまま社会全体が落ち込めば、当然安心できない時代に突入した感もあると思います。
会社員でも公務員でも同じだと思いますが、給料を5千円、1万円あげるということはどれほど大変な事か、実際お勤めしている方なら良くわかるでしょう。毎日朝早く起きて通勤し、人間関係のストレスに耐えて働いても、評価はなかなか上がらない。
このままでは、ただでさえ辛いお小遣いや家計の出費、住宅ローンや老後の備えに加え、不安定な消費税、その他税金などなど、年を追うごとに辛くなる一方です。
これも全ては会社、組織1つのみに生活全てを依存しているため。じり貧となる前に、今後は会社、組織以外にも収入源を増やしていく必要性が益々高まっているのかと思います。
今現在、私はそういった社会の先を見越して行動したいと思っている人向けに、自分の経験を通して無料のメールマガジンを配信しています。
詳しくは是非、以下を御覧くださいね。


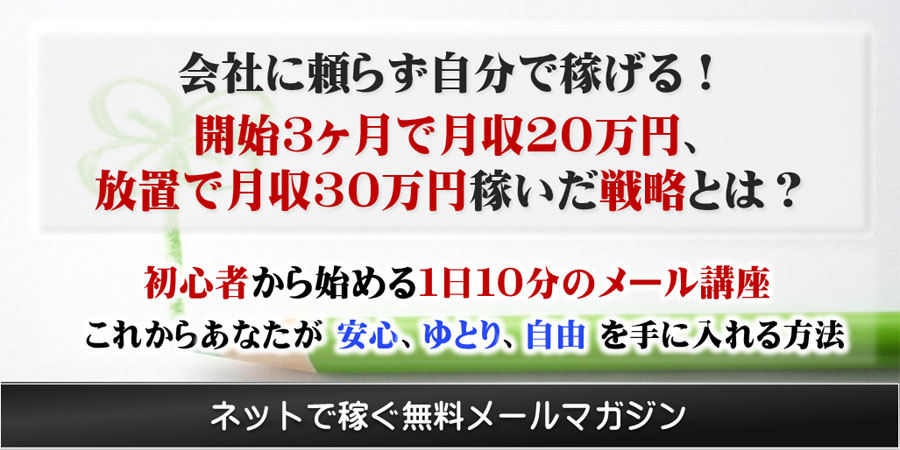
コメント